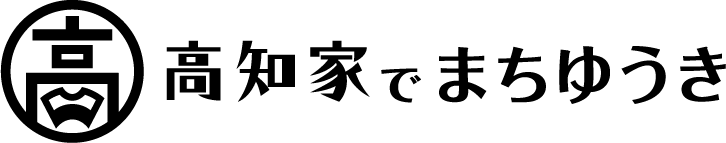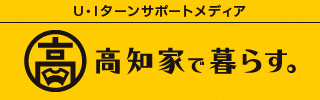東京から仁淀川町へ。「地元の人になりたい!」と飛び込んだ(仁淀川町)
- 2021年7月23日

小原 紀子(おばらのりこ)さん
北海道出身。大学卒業後は東京の出版関連会社に勤務。2014年10月に仁淀川町の地域おこし協力隊に着任。2017年9月に退任するまで、フリーミッションとして地域の集落活動センターの広報紙制作やイベントのお手伝い、ラジオ番組の台本制作などを実施。現在は、協力隊にいたころから付き合いがあった「トレトレ株式会社」に勤務中。近所づきあいを大切にしながら、自分のペースで楽しく生活しています。
小原 紀子さんにインタビュー (仁淀川町)
― 名無しの権兵衛から「小原紀子」になる!?
高知県を流れる仁淀川の上流域に位置する仁淀川町。高知県と愛媛県の県境に位置する自然豊かな里山の町に、小原紀子さんは暮らしています。小原さんが仁淀川町に住むようになったのは、2014年10月に地域おこし協力隊に着任してから。そのきっかけを聞くと、東京の暮らしに不安を覚えたからだといいます。
「私はもともと北海道出身です。東京の出版関係の会社で仕事をしていたんですが、住んでいた世田谷区には一人も知り合いがいなくて…。誰も自分のことを知らない環境は楽な反面、一生このままではよくないと思い、ガラっと生活を変えたくて移住を決めました」と振り返ります。
移住を考えたきっかけのひとつに、東京で経験した東日本大震災があったそうです。大きな災害があっても周りに知り合いがいなくて頼るところも、居場所もない。そんな「名無しの権兵衛」から、「小原紀子」という自分の輪郭をはっきりさせたい気持ちが強くなり、小原さんは東京を出る決意をしました。
「誰しもが認める地元の人になりたいと、一生骨を埋めるつもりで移住しました。未来のことはわからないですけど、ここを私の地元にしたい」と、小原さん。覚悟を決めて移住に踏み切った固い決意が伝わってきました。


― 山の魅力がいっぱいの仁淀川町に暮らす
まず、移住のために行動したのは、東京で開催していた高知の移住フェアへ行ったことでした。当初は高知市で就職しようと思っていた小原さんですが、それだとおそらく東京での暮らしと大差ありません。友達にも「市街地に移住するのは今とあまり変わらなさそう」と言われたこともあって、もっと田舎町に引っ越そうと考え直しました。
はじめは一般企業への就職を考えてみましたが、地域おこし協力隊の人に会って考えは変わりました。「協力隊って、何かを成し遂げたいという気持ちで入ってくる人もいるけど、そこまで気負わずに着任してもいいと思うよ。必ずやれることがあるよ」と、先輩協力隊員からのアドバイスを受け、実際に協力隊に挑戦してみることにしました。
仁淀川町を選んだ理由についてはこう話します。「地元の北海道には山が近くにあるんです。なので、私は海よりも山に馴染みがあるので、仁淀川町を選びました。ちょうど協力隊の募集があったのもタイミングがよかったです」。
そうそう小原さんが田舎暮らしで心配だったのが車の運転なのだとか。何年もペーパードライバーだったため、高知空港から2~3時間もかかるような高知県の東部・西部は運転技術的に難しいとも思ったとか。その点、仁淀川町は高知空港まで1時間半とちょっぴりアクセスしやすいところも魅力に感じたそうです。


― 地域おこし協力隊の支援から、退任後の就職先へ
2021年現在、地域おこし協力隊を退任した小原さんは、ヒノキを使ったミストや野草などを使ったブレンドティーなどの企画・製造・販売をしている「トレトレ株式会社」で働いています。実際に野草を摘むところから、パッケージデザイン、商品企画や取引先への対応と、一人何役もこなす小さな会社の大きな戦力です。
トレトレと出会ったのは、協力隊任期中のことでした。仁淀川町の「山の暮らし」をコンセプトに商品企画を検討していた代表の竹内太郎さんが、町内で「ハッパカイギ」と名付けたミーティングを開催していました。ハッパカイギは、地域の方々からお茶にする野草の情報を交換したり製品化への進捗を報告したりする場として定期的に催されていました。
小原さんも協力隊の業務の一環として顔を出すようになってから、商品を考えたり、野草を摘んだりと少しずつお手伝いをするようになり、協力隊卒業後、自然な形で就職が決まりました。

「もともと植物は詳しくありませんでした。でもいろいろ勉強もしながら野草の名前も覚えてきて、やっていること自体に面白さを感じて。仁淀川町の身の回りにあるものが製品になり、全国にお届けできていることにやりがいを感じています」と小原さん。
仁淀川町に限らず、小さな町では就職先を確保することもスムーズにはいきません。その点、協力隊の支援先から就職先が見つけられ、しかも自ら「やってみたい!」と思う仕事に就けていることは「幸せ」だと感じているそうです。

― おせっかいな人たちに囲まれて楽しく暮らす
最後に、仁淀川町での女性の一人暮らしについて聞いてみました。「今は、“小原紀子”ということで認識していただいているので、一人の人間としていられるような感覚があります」とのこと。東京にいたときの居場所のなさとは真逆で、地に足がついた生活ができている様子が伝わってきました。
車ですれ違ったら「昨日、○○へ行っちょったね」、部屋に電気が点いていれば「遅くまで電気が点いとったね」、そして出張などで車が置きっぱなしになっていれば「部屋のなかで倒れちょらんか心配しとった」と、小原さんの周りの人たちはいい意味で“おせっかい”。時には煩わしく感じてしまうこともあるそうですが、大らかでオープンマインドな人たちのコミュニケーションに助けられている部分が多くあります。
東京にいたときは人見知りで知らない人と話すのは苦手だったそうですが、高知に来てからはそうはいっていられません。協力隊に着任してからは、初めて会う人ばかり。いろんな人と意見交換をし、地域のお手伝いをしながら知らず知らずのうちに広がった「人の輪」が、女性の一人暮らしのお守りのような支えになっているそう。
2021年で仁淀川町に来て7年目。「最近は、移住してきた頃に感じていた『頑張らなくちゃ!』といった肩の力は抜けて、自然体での暮らしができるようになっています」と小原さん。地元の人と一緒に過ごす時間が増えて、次第に責任のある地区の区長も任せてもらえるようになったそうです。
「みんなから信頼してもらっているのかな?」とはにかむ表情に、仁淀川町での穏やかな暮らしがにじみ出ていました。